取引相場のない株式評価の改正(Ⅱ)
Ⅲ.2要素ゼロの会社の評価方法
今までは、「1株当たりの配当金額」、「1株当たりの利益金額」、「1株当たりの純資産額(簿価)」のうち、いずれか2つが3期(純資産価額は2期)連続ゼロのいわゆる ”2要素ゼロ“の会社の株式については、純資産価額方式で評価することとされていました。
しかし、今回の改正により、“2要素ゼロ”の会社の株式についても純資産価額方式だけでなく、納税者の選択により類似業種比準方式が適用できることとされました。
ただし、類似業種比準方式の割合は会社の規模にかかわらず0.25とされるので、評価額を計算する際の算式は、
![]()
となります。なお、3要素がゼロの会社については、従来どおり、純資産価額方式のみの適用となるので注意してください。
Ⅳ.適用の期日
この改正評価通達の内容は、原則として平成12年1月1日以後の相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価から適用されることになります。 ただし、12年7月31日以前に相続、遺贈または贈与により取得した非上場株式については、旧通達を適用してもよいこととされました。(説例2)
前回は、配当:資産=1:1で、利益の割合を変えて、改正前後で評価の額にどのような変化があるのかを検証し、比重の高くなる利益率が大きければ評価が高く、小さければ評価が低くなることを試算しました。今回は、配当比準値の高い場合と低い場合でどのように変わるのか検証してみます。
ここで、前回と同じ例で、配当比準値を変動させて考えてみます。仮に(類似業種平均株価)Aが200円の場合に利益、純資産額の金額を類似業種、評価会社を同額とし、類似業種の年配当額を100円(B)、評価会社の年配当額(b)だけを100円、0円、200円とした場合の類似業種比準株価はどのようになるでしょうか。
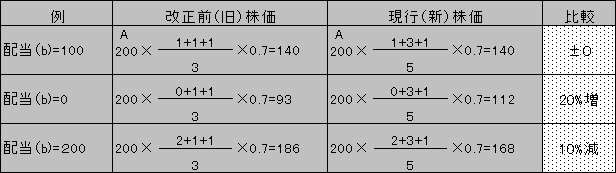
このように、資産:利益=1:1で、比重の大きい利益が平均程度であっても、配当率が小さいと、改正後の評価は逆に高くなります。改正前後の比較では、どうしても利益の割合に目がいってしまいますが、配当率でも評価が変わってくることは見落とせないポイントになっています。
暑さ寒さも彼岸までという諺は本当ですね。 信じられないような猛暑が9月に入ってもずっと続いておりましたが、先日の東海豪雨を境に徐々にやわらぎ、気がついてみると朝の空気のひんやりとした感じに秋の気配が漂っております。さあ、いよいよ天高く馬肥ゆる秋を迎えますが、一方で夏の疲れなどを引きずっていませんか。 1日の温度差もけっこうあり体調不良や風邪をひいてしまったという人も多いのではないでしょうか。 少しでも疲れが残っているようなら「コン」のつくものをたべることをおすすめします。
疲れきることを「精根つきる」といいますが、心身の力と根気がなくなった状態を表現する言葉です。 そこで根気を補給するために、「コン」のつく食べ物を口にして、元気を回復してください。これは単なる語呂合わせではありません。語呂としても面白いのですが、それだけの理由ではないのです。
「コン」と名のつくものとは、ダイコン、レンコン、ゴンボウ(ゴボウ)などのことで、いずれも食物繊維が多く含まれていて、体内を浄化し、血行をよくする作用があります。ですから、これらを食べることで、自然に疲れもとれてきます。
とにかく、食事というものはバランスが大切です。めんどくさい、好きだからといって、同じパターンの食事ばかりしていると、食べ物のバランスを失い、体をこわす原因になります。
そこで、夏バテの解消策として、日頃食べないものを食べるとうことも一理あることになります。
もちろん、こういった口から入れる栄養だけでなく、頭が求める読書といった栄養、あるいは日常のビジネス行動の中で、ニガ手なものにあえてチャレンジするという精神栄養も大切です。
ともあれ、実りの多い秋にするために、1つでも多く身体にいいこと、心にいいことを実践したいものです。
( 所長 橋本 )この様に改正前と改正後との比較では、利益が大きければ評価額も高めとなり、低収益であれば評価額も逓減し、利益比準値を重視する計算に改正されました。 更に斟酌率が中会社、小会社では、一層加味されることになります。