インローについて
|
| カタカナでインローと書くとピンと来ませんが、「印籠」と漢字にしますとイメージが沸いてきます。 |
|
| 日本建築の最大の特徴は、継手と仕口の手法を用いる事だと言われています。 |
| さまざまな継手の中に「印籠継手」があります。 |
| 以下、引用文献:「図解 木工の継手と仕口」著 鳥海義之助 |
 |
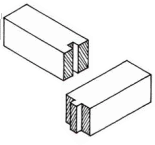 |
目違(めち)入れは
印籠(いんろう)継ぎともいい、
ほぞは
めちほぞと呼んでいる。
平易な目違い継ぎである。 |
| 印籠目違い継ぎ |
|
 |
|
|
| ■継手 |
| つぎ手は、ものとものとを接合するときの手口(joint)を意味し、 |
| 継手または接手と表記されています。 |
| 継手は突付けつなぎを指し、接手は切り組みものを指すとする説、 |
| 両者を区別せず、継手と仕口とを分ける説など、いくつかの考えかたがあります。 |
| 木工の世界では、同じものでも地域や職種によっては違った呼びかたをしますが |
| 呼称は違っても意味は同じである場合が多いです。 |
 |
| ■仕口 |
| 仕口は指し口、差し口ともいいますが、木工でも職種により口伝もあり、 |
| 同じ意味でも呼称が違うことがある。 |
| 仕口には平易なものから複雑なものまでいろいろありますが、本来 |
| 仕口こそ木工の技術そのものであったということができましょう。 |
 |
| ■余談になりますが TV水戸黄門の印籠に関する記事を転載させていただきました。 |
〈10〉2005/10/12付北國朝刊----------------------------☆
◎輪島塗の印籠を制作 輪島市の製造元 時代劇「水戸黄門」で使用
輪島市長井町の輪島塗製造元「うるしのともゑ」は、10日から
北陸放送などTBS系で放送が始まった時代劇「水戸黄門第35部」で
使用されている輪島塗の印籠(いんろう)を制作した。
11日、若島文久専務取締役(41)ら4人が輪島市役所に大下泰宏助役を
訪ね、制作した印籠の写った番組パネルを寄贈した。
印籠は若島宗斉代表取締役(65)が手掛け、葵(あおい)紋に
高蒔絵(たかまきえ)を施すなど伝統の技法を駆使し、約2年の歳月を要した
普段は専用の金庫に保管され、手袋をはめて取り出すなど慎重に
取り扱われているという。若島代表取締役は「国民的番組に携われて光栄。
輪島塗の普及に役立てばいい」と話している。
|
| ■印籠の製作が書かれたHPを見つけました。大変多くの工程があるようです。 |
| http://www16.plala.or.jp/shokyuan/inrou-seisakukoutei.htm |